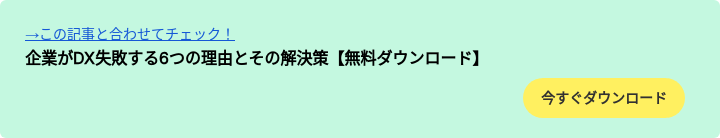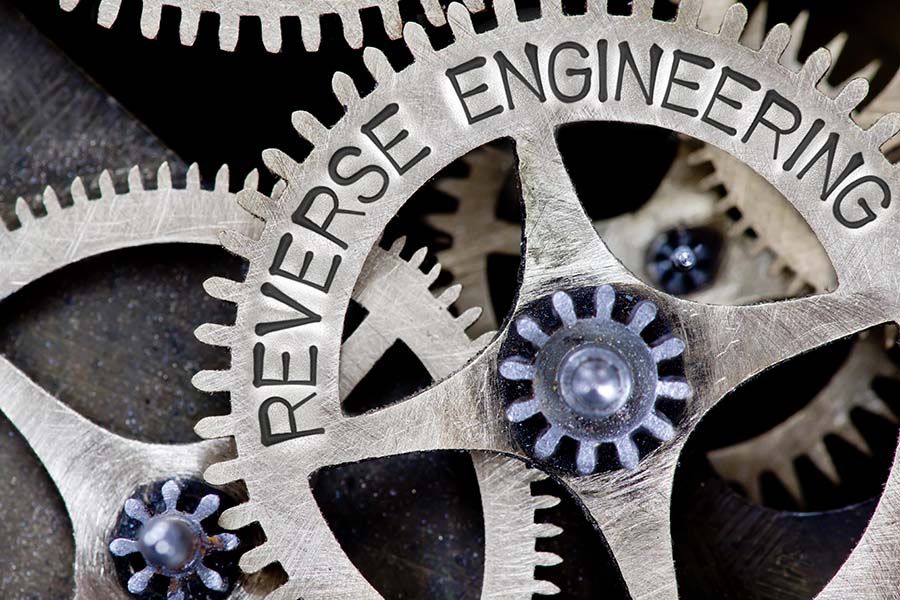オンラインでの顧客行動をオフラインでも生かす「O2Oマーケティング」について知る人は多いでしょう。例えば、ECサイトを訪れたユーザーに実店舗で利用できるクーポンを配布して、デジタルからリアルへと行動を誘導します。こうしたマーケティング施策はスマートフォンが普及する以前から取り組まれてきたものであり、2013年ごろから徐々に増加しました。
オフラインとオンラインの両軸でさまざまな販売チャネルを設ける「オムニチャネル」も普及しており、1つのブランドが複数の販売チャネルでビジネスを展開することも珍しくなくなりました。店頭へ行く時間が取れない方も、自宅でオンラインショッピングを経験したことがあるでしょう。
今回ご紹介するのは、このO2Oではなく「OMO」です。世界最大のEC市場を形成する中国で誕生したこのマーケティング概念とは一体どういったものなのか、分かりやすく解説します。
OMOとは?
中国では「スマートフォン1つあれば生きていける」というほど、モバイル中心の生活を送っている国民が多数存在します。また、日本のようにクレジットカード決済が普及しておらず、「Alipay」などのモバイル決済が基本となっています。ECサイト市場における流通総額のうち、90%以上がモバイル経由というのも圧倒的な数値です。
オンラインとオフラインの連携が日本以上に進んでいる中、両者の境界線がなくなってきている状況から、O2Oの考え方を発展させたOMOに概念が切り替わりつつあります。OMOとは「Online Merges With Offline」の略であり、日本語に言い換えると「オンラインとオフラインの融合」となります。
OMOとO2Oの違い
O2Oはオンラインとオフラインという2つの世界を切り分けて考え、双方間の行き来を促すというマーケティング施策です。それに対してOMOは、オンラインとオフラインの境にこだわらずに、あくまでUX(顧客体験)に主眼を置いています。消費者のあらゆる行動をデータとして集約し、UXを向上するためのマーケティング施策を展開するのがOMOです。
それはオンラインとオフラインに関係なく、消費者にとってその都度適切なチャネルで最適な情報を届け、顧客体験を向上させていこうという非常にシンプルなマーケティング概念です。
OMOとオムニチャネルの違い
オムニチャネル(Omni Channel)の「オムニ(Omni)」とは「全て」という意味を持つ言葉です。オムニチャネルとは、実店舗のオフラインチャネルとECサイト、アプリ、テレビショッピングなどのオンラインチャネルに販売チャネルを設けたものです。どの販売チャネルにおいても顧客データや購買データを収集し統合的な販売戦略を実現するための概念がオムニチャネルです。
OMOとオムニチャネルとの違いは、オムニチャネルではオフラインとオンラインを区別するところにあります。また、企業の視点で顧客との接点を増やします。
中国のモバイル事情
モバイルペイメントが急速に普及したこともあり、中国都市部では現金を持ち歩かないことが常識になっています。それはつまり、消費者が行う移動や食事、ショッピングやレジャーなどのオフライン行動のほとんどが、分析可能なオンラインデータとして個別IDに紐づけられて蓄積されていくということです。
都市部のスーパーでは、商品に付属している二次元コードを読み取ると、商品の詳細情報や購入者のレビューをその場で確認できます。この行動によって、実店舗で商品を見て、詳細情報を調べ、レビューを確認したというデータが個別IDに紐づけられて蓄積されます。このほか、スマートフォンアプリを使って行ったショッピングや閲覧したセール情報、実店舗におけるモバイル決済や購入したものなど、あらゆる消費者行動がデータとして活用可能です。
膨大な消費者データをある属性にセグメントして分析するのではなく、あらゆるデータを個別IDに紐づけた状態で個別に分析を行うことで、消費者ごとの嗜好を理解した上で適切なマーケティング施策を展開できるようになるのです。
このように、消費者の行動がその時オンラインにあろうがオフラインにあろうが、一貫したUXを生み出すのがOMOの考え方です。
小売業界におけるOMOの重要性

経済産業省が2022年に発表した「電子商取引に関する市場調査」によると、物販系分野におけるEC事業の売上は2021年に13兆2,865億円に到達しており、EC事業の市場規模は年々右肩上がりで拡大していることが分かります。
消費者にとって、ECサイトをはじめとするオンライン環境で時間や場所を選ばずに商品を購入することはもはや日常となっており、企業はオフラインやオンラインの環境を区別することなくシームレスな顧客体験を提供することがますます重要となってきています。店舗で商品を購入してもアプリやECサイトで商品を購入しても、差分のないブランド体験を消費者に提供することが求められています。
OMOを実現することによるメリット

身の回りを見渡すと、OMOを導入している企業はいくつも見られます。店舗とアプリで同じ商品を購入できることも珍しくなくなりました。OMOには具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
機会損失を最小限に抑えられる
オンラインやオフラインを問わず顧客と接点を持つことができるため、顧客は時間や場所を選ばずに商品を購入することが可能です。
例えば、衣服を購入したい場合、外出して店舗へ赴くことなくオンラインショップで購入できます。仕事でプライベートな時間に制約がある人にとっては便利でしょう。家で好きなレストランのメニューを食べたい場合には、デリバリーで注文すれば店舗へ出向く必要はありません。
質の高い顧客体験を提供できる
さまざまな販売チャネルから顧客の属性データや購買履歴を統合的に集約し、分析することで、企業は顧客に応じたメッセージを発信できるようになります。
例えば、特定ブランドのスニーカーを購入する頻度が高い顧客には、そのブランドのスニーカーに関するDMやアプリのプッシュ通知を送れば、顧客に興味のある情報を届けることができます。言い換えれば、その顧客にとって興味のない情報を発信しないことで顧客体験の質を維持できます。
ブランドイメージの向上につながる
オンラインやオフラインを問わず、ブランドとして統一されたメッセージを発信することでブランドイメージの向上につなげることができます。もちろん、ブランドイメージの向上には、ブランドガイドラインのような一定のポリシーを定め、それに基づいたメッセージの発信が前提です。
また、OMOにおける顧客に対するメッセージは、さまざまなタッチポイントから収集した顧客データを元にパーソナライズ化され、適切なタイミングと接点を通して発信されることで、ブランドイメージの向上につながるでしょう。
リピーター施策になる
さまざまなタッチポイントから得た顧客データを活用することで、顧客の趣向に応じたマーケティング活動ができるようになります。
顧客に応じた適切なアプローチによってLTV(顧客生涯価値)を高めることが可能です。例えば、商品の購入を通じてポイントを付与し、一定のポイントがたまると特別なクーポンや特典と引き換えができるロイヤリティプログラムなどがあります。新規顧客の獲得が難しい市場では、LTVは重要な指標です。
OMOの導入前に理解しておきたいデメリット

OMOを実現することのメリットは企業にとって大きいですが、デメリットも無視できません。OMOの導入や実施には乗り越えなければならないいくつかのハードルがあります。この章では、OMOのデメリットについて解説しましょう。
すぐに効果が現れるわけではない
OMOを通じて得られる顧客データを具体的なマーケディング活動として活用するには、長い時間をかけてデータの収集や分析を行う必要があります。そのため、短期的に売上を上げる即効性はOMOに期待できません。
顧客の購買性向や行動傾向は長期的なスパンで捉えることで初めて見えてくるため、LTVを上げるための施策を実行したとしても、それが必ず成功するわけではないのです。試行錯誤を経て、一定の成功法則を見つけていきましょう。
効果の大きさはビジネスモデルにより異なる
OMOは、オフラインとオンラインを横断して販売チャネルに捉われることなく顧客にアプローチする概念です。そのため、どちらか一方のみのビジネスモデルではその効果を実感しにくい点があります。
例えば店舗型のみのビジネスを展開するケースでは、顧客から得られる属性データに限界があり、購買データとうまく結びつけることが難しいです。OMOに活用できるデータ量が乏しいと、データを活用した施策の数を増やすことができません。
社内体制やシステムを整備する必要がある
OMOの実装には予算と工数がかかります。OMOを実現するための戦略策定、予算承認、開発時のシステム要件定義、公開前の社内メンバーに対するトレーニングなど、さまざまなステークホルダーを巻き込んだ大きなプロジェクトです。
社内に開発する部署がない場合は、社外のベンダーと協業してプロジェクトを進めていくことになります。このように、OMOを実現するには長期間にわたって多くの工程を経なければなりません。
OMOの成功のために必要な対策

OMOを通じてビジネスを拡大していくには、実装しなければならないことがいくつかあります。OMOは手段であり、目的ではないことを念頭におきつつ、ここではOMOにおける主要な4つの対策について解説します。
販売チャネルを広げる
インターネット環境が整備されスマートフォン端末が普及したことにより、昨今の消費者行動においてアプリやECサイトを通じたオンライン購入は日常となっています。消費者のさまざまなライフスタイルに合わせて場所や時間を選ぶことなく商品を購入できるよう販売チャネルを広げる(マルチチャネル化する)ことは、ビジネスを拡大する上で重要です。
複数のICTを導入する
ICTとは情報通信技術(Information and Commnunication Technology)のことを指します。OMOを活用した顧客のLTV向上やブランドイメージの向上を図るには、デジタルを駆使したデータ活用が必須です。
データ活用には、顧客に合わせたコミュニケーションを実現できるMA(マーケティングオートメーション)ツールや、CRM(顧客管理システム)などのデジタルツールの導入が必要となります。
データを一元管理する
自社アプリやWebサイトにおける行動ログや、販売チャネルを通じて得られる購買データはDWH(データウェアハウス)と呼ばれるサーバ上で一元管理します。収集したデータは、活用できるようにするため顧客IDごとに整理します。
整理したデータは、MAツールやCRMと連携することでマーケティング施策や顧客対応に活用したり、BIツールへデータ連携することで顧客の購買分析をより緻密に分析したりできるようになります。
接客の質を向上させる
デジタル技術によるOMOの浸透は、実店舗における接客対応の質を向上させることができます。
あるアパレル企業では、自分が欲しい商品が店内のどこにあるのかをアプリ上の地図を見るだけで分かるようにしています。店員の数が限られる店舗において、こうしたデジタル技術の活用によって顧客のニーズに応えることで、接客の質向上に貢献できるのです。
OMO先行事例
中国では、検索エンジンのシェアトップのBaidu、ECモール大手のAlibaba、そしてSNSなどのWebサービスを幅広く提供するTencentが「3大インターネット企業」です。このうちTencentは、「WeChatPay」という独自決済サービスを中国全土に普及させています。中国版LINEとも呼ばれるWeChat(微信)に付随する決済機能であり、EC決済や店舗決済だけでなく、個人間送金にも利用されています。
Tencentが2017年に打ち出したOMO施策が、スマートフォンへのダウンロードおよびインストール不要の「ミニプログラム(小程序)」と呼ばれるサービスです。例えば電車の発着時刻を知りたい場合は、専用アプリをスマートフォンにインストールして、アプリを起動して時刻を確認します。一方ミニプログラムでは、駅に用意されている二次元コードを読み取ることで電車の発着時刻を知ることができるのです。WeChatがあれば、いろいろなアプリをインストールする必要はありません。
さらにTencentは、飲食業界におけるOMOにも積極的に取り組んでいます。2018年5月に鴨肉加工食品の小売店である「周黒鴨」とWeChatPayが連携し、「周黒鴨×WeChatPay」のスマート店舗がスタートしました。消費者が初めて店舗へ入店する際に、WeChat上でアカウントを作成して顔認識を行えば、次回以降は顔認識のみで入店できるようになります。会計は、セルフレジに商品を置くだけで完了。目の前に設置されたカメラが消費者の顔認証を行い、WeChatPayによりその場で決済されます。
中国都市部では同様のスマート店舗が急増しており、スマートフォンでQRコードをスキャンするという行動すらなくなりつつあるのが現状です。
このように、モバイルペイメントと消費者に紐づけられたデータに加え、AIやIoTといった革新的な技術を搭載したサービスを提供することで、消費者はこれまでに体験したことのない新しいUXを得ることができます。
OMOで大切なのは徹底したUX設計
UXを重視するマーケティング施策は、日本でも盛んに行われています。しかしその多くはオンラインに限定されたもので、消費者が商品の認知や情報収集、購入に至るまでのプロセスでUXを改善するというよりは、商品の見せ方やWebサイトのレイアウト、あるいは店舗設計などに重点が置かれているようです。
中国で急速に進んでいるOMOの基本は、「徹底したUX設計」です。そこにはオンラインもオフラインもなく、よりよい商品の見せ方や店舗レイアウトもありません。大切なのは「どうすればUXが改善され、消費者は先進的でより良い体験ができるか」を考えることなのです。
こうした考え方を根底に据えることで、マーケティング施策をオンラインに限定せず、広い購買プロセスの中で最適な施策が展開できます。
また日本でも、急速に進んでいる中国EC市場を対象にした越境EC事業においてもOMOが重要になっています。日本のLINE Payは2019年にWeChatPayと連携し、インバウンド需要強化に向けた取り組みをスタートしました。つまり、中国の消費者の個別IDに紐づけられたさまざまなデータを日本企業が取得できるようになるということで、越境EC事業においてそのデータ活用が極めて重要になっていきます。
今こそ日本企業でもOMOを推進して、一貫性と質の高いUXを提供しなければいけない時です。自社に蓄積している消費者データに加え、オンラインとオフラインで提供している各チャネルを活用することでどんなOMO施策を展開できるのかを、今考えてみてほしいいと思います。
まとめ

誰もがスマートフォン端末を利用し、インターネットを通じて商品を購入することが当たり前となった現代において、もはや消費者における購買行動はオンラインとオフラインの境界が曖昧になりつつあるといえます。小売業におけるOMOの実現は、このような時代の潮流に遅れないための必須概念です。
まずは、競合他社がOMOにおいてどのような施策を実施しているのか研究してみるところから始めてはいかがでしょうか。