「デジタル変革」と日本語で訳される「DX(Digital transformation)」は、企業のマーケティング活動を根本から変えようとしています。 人々の生活の変革を目指すDXが注目を集めている背景には、顧客が新しい価値観を求め始めたことがあるようです。
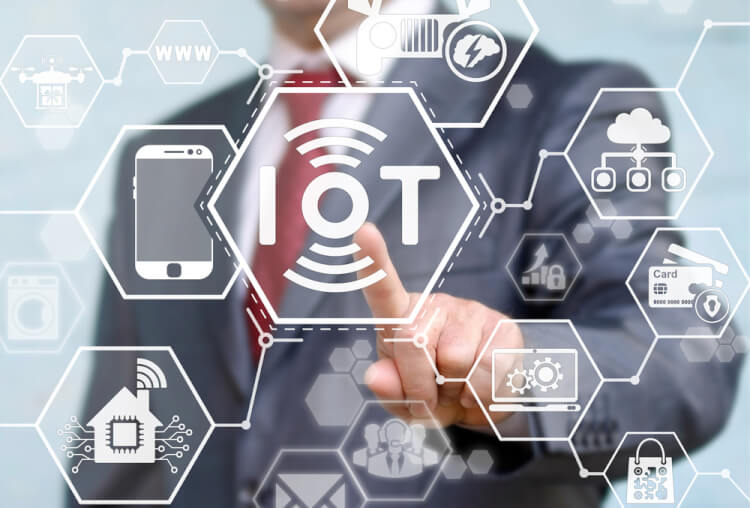
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、「IT技術により人々のあらゆる体験を良い方向に変化させること」と定義することができます。
「DX(Digital transformation)」の日本語訳「デジタル変革」のとおり、AIや IoT などのIT技術により、人々の生活を変革させることを目指す概念です。
データとIT技術を駆使して、新たな顧客ニーズを発掘し、顧客満足度の高い商品やサービスを提供できなければ、企業は生き残れない時代になっているといえます。
電通デジタルが主導で実施した「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2019年度)」によると、日本企業の70%がすでにDXに着手していると回答しています。
具体的な取り組みの内容は、データ活用戦略の策定や組織・人材開発などが中心となっており、中長期的な計画の中でDXに取り組む企業が多いと想定されます。
また、企業全体でのDXを牽引する人材として期待が高まっているのが、CDO(最高デジタル責任者)です。
前出の電通デジタルによる調査の中で、DXを牽引すべき役職者は誰かという質問では、2018年度には15%がCDOと回答しましたが、2019年度はさらに3ポイント増加し、18%がCDOと回答しています。
新たな価値観への転換期
DXの考え方が急速に浸透し、各企業もDXに取り組む理由として、顧客に新たな価値観が生まれており、消費行動が変化していることが挙げられます。
マスマーケティングと呼ばれたように、かつては大量生産・大量消費の時代で、大勢の顧客に対して画一的なマーケティング活動を行っていれば、商品が売れていました。
しかしITが発達し、誰もがスマートフォンで商品に関するあらゆる情報を収集できるようになった今日、顧客は商品が購入できるのは当たり前と考え、購入に至るまでの体験にも価値を求めるようになりました。
「モノ消費」から「コト消費」へと、消費に関する価値観が変化しており、この「コト消費」の価値観で必要不可欠なのが、デジタル変革・DXです。 企業は今後、様々なデータを収集・駆使して、新しい商品・サービスと同時に新しい体験を生み出さなくては生き残れなくなるでしょう。
DXへの5つのステップ
DXはどのような手順で導入すればよいのでしょうか。DXには、デジタル化から最適化まで5つのステップがあります。
1:デジタル化
DX導入の最初のステップは、社内に蓄積しているあらゆる情報をデジタルデータ化することです。
紙で保存されている情報など、企業全体の情報資産としては機能していないものも含め、デジタルデータとして蓄積します。
勤怠管理や経費管理などはシステム化することで、そこに入力される情報すべてを企業の情報資産として蓄積できます。
ステップ1は、デジタル技術導入の初期段階で、自社のWebサイトを開設するような限定的なデジタル化が行われている状態です。
2:効率化
ステップ2は、蓄積したデータを部門や部署内などの限られた範囲で活用し、業務効率化につなげる段階です。
例えば、営業部門でデータ化した勤怠管理情報と各営業部員の営業成績とを比較して、非効率な活動がないかをチェックするといった活用法です。
この段階では、運用ルールは各部門で決定し、他の部門とは共有化されていない状態です。
日本国内のほとんどの企業が、まだステップ2の段階にあるとされています。
3:共通化
ステップ3は、部門をまたいでデータを活用するための共通基盤を作り上げる段階です。
営業部門が取得した新規顧客に関する情報は、マーケティング部門はもちろん、商品開発部門においても役立つ情報でしょう。
複数の部門をまたいでデータを活用するためには、共通の基盤が必要になります。
共通基盤は、仮説に基づいて対策を実行したあと、検証するというサイクルを繰り返しながら構築します。
この段階では、関連する数部門でデータを共有し活用している状態です。
4:組織化
ステップ4の組織化は、ステップ3で構築した共通基盤を活用した組織づくりの段階です。
組織全体で運用するステップにあたり、デジタル化の専門部門を設置し、データ運用フローを明確にします。
この段階では、データを活用した効率化がすでに定着しており、次のイノベーションを起こすステップに向けた仮説づくりを行います。
5:最適化
ステップ5は、DXの最終段階にあたり、デジタル技術が企業の基盤となっている状態です。
デジタル技術の活用を基本とした事業計画を立案し、事業のイノベーションを起こす施策が計画に盛り込まれます。
この段階では蓄積したデータをもとに、事業計画自体の精度を高めていくことも可能になっています。
DXを他社に先駆けて導入した企業でも、ステップ5の段階にはほぼ到達していません。
企業におけるDXの活用事例
DXによるマーケティング戦略で成果を収めている企業が複数登場しています。DXの活用事例を紹介します。
日本コカ・コーラ
日本コカ・コーラは顧客体験の向上を目標に、アプリ「Coke ON」を提供しています。
専用のスマート自動販売機で商品を購入したとき、自動販売機に「Coke ON」をかざして接続すると、商品1本につき1スタンプが加算されます。
15スタンプがたまるとドリンク1本分の無料チケットがもらえる仕組みです。
無料チケットは自分が商品に交換するだけでなく、友達に贈ることもでき、アプリを通して消費者同士のコミュニケーションも促進している好例です。
また、自動販売機でドリンクを購入する顧客は、ほぼ毎日購入するという、日常の習慣を利用していることも成功の一因だったようです。
「Coke ON」は、自動販売機をIoTマーケティングに活用した、世界で初めての事例としても有名です。
三越伊勢丹ホールディングス
商品を自分の手に取って確かめてから購入できるのが、ECサイトにはない実店舗の強みです。
三越伊勢丹も多くの実店舗を展開していますが、地方の店舗の品ぞろえは伊勢丹新宿本店や三越銀座店などの基幹店舗には遠く及びません。
また、各店舗では在庫を持たないため、顧客が求めているサイズや色が店頭にないこともあります。
そこで、三越伊勢丹グループはDXを活用して、基幹店にあるすべての商品がECサイトでも地域店でも購入できるようにする取り組みを開始しました。
具体的には、最も品揃えの良い伊勢丹新宿本店の店舗に並ぶ商品をデータベース化し、各取引先と商品情報や在庫情報を連携して、基幹店の品ぞろえをWeb上で実現するのが目的です。
資生堂
資生堂は、IoTスキンケアシステム「オプチューン」を展開しています。
「オプチューン」は月額の定額プランになっており、会員登録をするとスキンケア専用マシンとカートリッジが自宅に届きます。
会員が専用アプリ「Optune app」を顔に当て、その日の肌の状態を測定すると、「オプチューン」が肌の水分や毛穴の状態だけでなく、気温や紫外線などの外的要因までも考慮して、最適なケアを決定します。次に、利用者が自分の手を専用マシンの下に差し出すと適量の肌ケア剤が抽出される仕組みです。
「オプチューン」は、これまでは美容部員が行っていた顧客への肌ケア提案を、IT技術で再現したものです。 肌ケア提案の組み合わせは8万通り以上あり、資生堂の持つ知見をデータ化して分析・活用することで、このような詳細な提案を実現しています。
まとめ
「モノ消費」から「コト消費」への価値観の変化に対応するには、DX導入が必要不可欠となっています。DXを活用した新しいサービスや商品はすでに生まれており、今後は、多くの企業が追従しDXを推進するとみられています。
これからDX導入を検討する企業においても、ステップ1のデジタル化から着手すべきときが来ているといえるでしょう。












