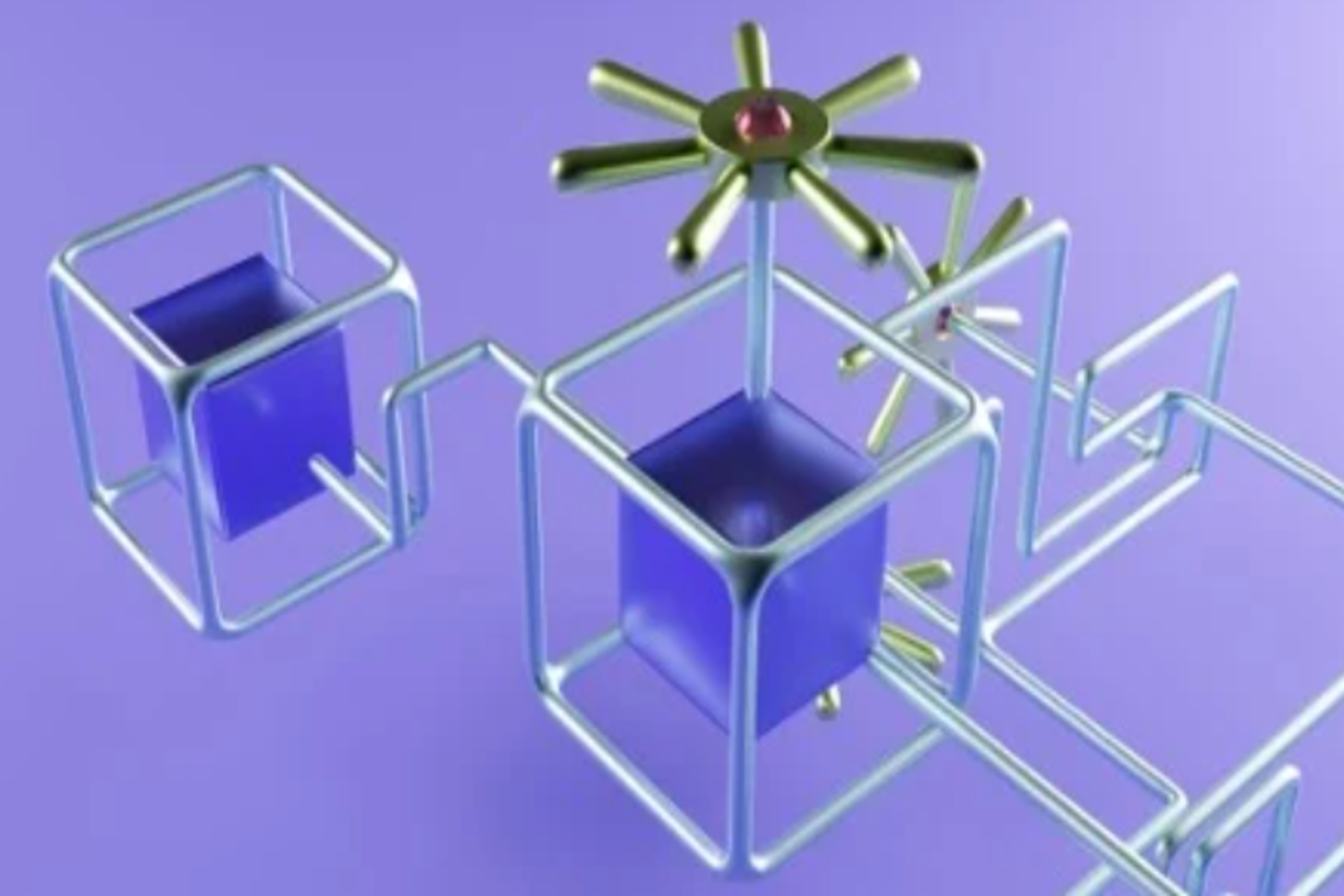コンテナ型仮想化を活用することで、少ない物理マシンで効果的にシステムを運用することができるようになります。しかし、コンテナ型仮想化の仕組みやメリットはまだ十分に認知されていません。そこで本記事では、コンテナ型仮想化の概要やメリット、またCTCが提供するC-Nativeのサービスについて解説していきます。
.jpg)
コンテナ型仮想化とは
「コンテナ型仮想化」とは、仮想化技術によって、1つのホストOS内に、複数の独自環境を構築することを意味します。この仮想化された独自環境に相当するのが「コンテナ」です。コンテナ内ではさまざまなマイクロサービスやアプリケーション・ソフトウェアの実行が可能です。
従来のシステム構造は、1台の物理マシンに対して1つのOS、そして1つのOSに対して1ユニットのアプリケーション・ソフトウェア環境を割り当てて運用するのが通例でした。しかしコンテナ技術を活用することで、1台の物理マシン上で複数のアプリ環境を集約して起動・運用することが可能になります。コンテナ型仮想化を実現するサービスとしては、後で紹介するC-Nativeなどが挙げられるでしょう。
コンテナ型仮想化を含む仮想化技術は従来、ソフトウェア開発者などを中心に重宝されてきた技術です。しかし最近では企業の基幹システムがクラウドベースに移行し、テレワークの導入も増えてきたことで、テレワーク環境の構築のために有用な方法としても注目を浴びつつあります。
ハイパーバイザ型仮想化との違い
同じ仮想化技術でも、コンテナ型仮想化は従来のハイパーバイザ型仮想化(VN型仮想化)とはいくつかの点で大きな違いがあります。
ハイパーバイザ型仮想化は、ハードウェア上に複数の仮想化サーバないしは仮想化マシンを構築して複数の独自環境を起動・運用する方法です。一見すると、これはコンテナ型仮想化と変わらないように見えるかもしれません。しかし、コンテナの場合は独立環境と言っても根本のOS自体はホストOSに依存するのに対して、ハイパーバイザ型の場合は共用のホストOSを持たず、仮想化サーバごとに個別のOSを割り当てることによって、複数のOS環境の仮想化をすることが可能です。
ハイパーバイザ型仮想化ならば、例えばWindows OSとLinux OSそれぞれのシステム環境を同一ハードウェア内に共存させることもできます。これはコンテナ型仮想化にはない特徴です。これだけ見ると、ハイパーバイザ型仮想化の方がコンテナ型仮想化よりも優れた手法のように思えるのではないでしょうか。
しかし、ハイパーバイザ型はいわば、1つのハードウェアに物理マシン複数台分の機能を丸ごと搭載するようなものです。それゆえ、システムリソースへの負荷が非常に大きく、オーバーヘッドのリスクも高まります。これに対して、各コンテナがアプリケーションレイヤーで分離しているコンテナ型仮想化は、システム負荷が小さく、オーバーヘッドのリスクも軽減できます。
また、ネットワーク面でも、コンテナ型とハイパーバイザ型では仕組みが異なります。ハイパーバイザ型の仮想環境のネットワーク構成は、物理マシンと同じ扱いになるので、従来通りのIP管理が可能です。一方コンテナ型では、ハイパーバイザ型とは異なり、「コンテナごとにIPアドレスを自動設定する」「NAT(Network Address Translation)を使わないと外部通信ができない」などの特徴があります。
コンテナ型仮想化を利用するメリット
コンテナ型仮想化を利用するメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか。以下では、ハイパーバイザ型仮想化との違いも踏まえつつ、コンテナ型仮想化のメリットについて解説していきます。
アプリケーションを簡単、迅速に起動可能(高速)
コンテナ型仮想化を利用するメリットとして、アプリケーションを簡単かつ迅速に起動可能な点が挙げられます。ハイパーバイザ型仮想化の場合、システムを起動する際には、複数のOSの準備が並列して行わるため、ときには数分間も必要なほど起動時間が長くかかってしまいます。しかし、ホストOSのカーネルを共有するコンテナであればシステムリソースの節約ができるので、より迅速なシステム起動が可能です。
この速度の違いは、起動時だけでなく、システムの全体的な反応速度として現れる場合もあるでしょう。また、コマンドライン一つでコンテナを迅速に作成・破棄できたり、移行できたりする取り回しの良さもコンテナ型仮想化の魅力です。
リソースを節約し、効率的に利用可能(軽量)
複数OS分のシステム負荷が重くのしかかるハイパーバイザ型仮想化と比較して、ホストOSのカーネルを共有できるコンテナ型仮想化は、CPUやメモリといったシステムリソースを節約し、効率的に運用可能です。
当然ながら仮想化によるシステム負荷は、仮想化環境の数が多くなればなるほど重くなります。そのため、例えばテレワークにおける一般事務など、多くの人間が同一OSでシステム運用するような状況が想定される場合は、「ハイパーバイザ型よりもコンテナ型の方がシステム的なコストパフォーマンスに優れる」と理解していいでしょう。
アプリケーションパッケージ化によりどこでも起動可能(可搬性)
コンテナ型仮想化を利用するメリットとしては、その可搬性の高さを上げることもできます。コンテナ型仮想化を活用すれば、アプリケーションをパッケージ化してどこでも起動可能です。アプリケーションレイヤーでの分離によって軽量なコンテナは、オンプレミス環境はもちろん、さまざまなパブリッククラウドへの移行も容易に行えます。
これによってユーザーは、物理インフラに縛られず、さまざまな場所でアプリケーションを利用することができます。
「C-Native」でコンテナ型仮想化を実現
このようにコンテナ型仮想化は、従来のハイパーバイザ型仮想化とはまた異なった魅力を持つ仮想化方法です。コンテナ型仮想化を支援するソフトウェアはすでに複数ありますが、ここでは「C-Native」の紹介をしましょう。
C-Nativeは、 クラウドネイティブ 製品やIT関係のコンサルティングサービスを提供する伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)が提供するコンテナ仮想化活用サービスです。
C-Nativeを利用することによってユーザーは、コンテナ型仮想化の導入・移行・運用支援など、コンテナ型仮想化を活用する上で必要な包括的支援を受けることができます。C-Nativeを導入することによって、アプリケーション起動に必要なアプリ本体のほか、ライブラリや設定ファイルなどをひとまとめにした「コンテナ」を作成し、「コンテナエンジン」上で稼働させることが可能です。
クラウドネイティブフォーカス
C-Nativeの大きな特徴は、それが「クラウドネイティブフォーカス」な技術であることです。クラウドネイティブとは、クラウド上での利用を前提として設計されたシステムやサービスを意味します。近年、ITインフラを従来のオンプレミス環境からクラウド環境に移行させる企業が大きく増加傾向です。そして同時に、自社の基幹システムをクラウドベースでの運用に最適化したシステムに置き換えたりもしています。クラウドネイティブにフォーカスしたC-Nativeは、まさにこうした時代の潮流にマッチしたものと言えるでしょう。
C-Nativeはユーザー企業の社内システムとクラウドとの連携を支援し、既存のアプリケーションをクラウドネイティブ化することも可能にします。コンテナをベースとしたC-Nativeを活用することによって、ユーザーは拡張が可能なアプリケーションの構築や実行が容易にできるのです。
効率化に基づいたサービス提供
CTCはITソリューションの提供について優れた実績を持った企業であり、その豊富なノウハウを活かして十分な実績や検証を得た技術を提供しています。CTCはC-Nativeのサービス提供を通じて、自動化・自律化などに関する高度な方法論を活用し、ユーザー企業の競争力向上を強力に支援してくれることでしょう。このようにユーザー企業は、C-Nativeの利用を通して効率性に優れたサービスを受けられます。
ベストプラクティスの提供
C-Nativeはその豊富な実績とノウハウに基づいて、特定のベンダー企業の製品群や運用方法などに縛られないオープンな視点でサービスを提供しています。これによってユーザー企業は、ハイブリッド・マルチクラウドの実現や、その更なる高度化に向けて、自社に最適化された独自のソリューションを模索することが可能です。CTCは自社の研究センターなどでの検証・導入実績をさらに蓄積していくことによって、今後もさらにサービスの品質を向上させ、ユーザーにベストプラクティスを提供することでしょう。
まとめ
従来のハイパーバイザ型仮想化に比べ、コンテナ型仮想化はシステム的な負荷も小さく、取り回しのよさが魅力の仮想化方法です。特にクラウドベースでのコンテナ型仮想化の導入を検討している企業にとって、クラウドネイティブにフォーカスした「C-Native」の利用は有力な選択肢となるでしょう。