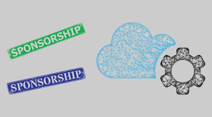クラウド移行 が自社ビジネスにどれほどの効果を及ぼすのか、検討したい社内IT部門担当者は多いのではないでしょうか。クラウド移行のROIの計算方法がわかれば、クラウド導入実施の必要性について、社内での意思決定がしやすくなるはずです。当記事では、クラウド移行におけるROIの考え方について詳しく解説していきます。

そもそもROIって?
「ROI(Return On Investment)」とは、投資に対する収益を比率で表した指標のことで、「投資利益率」や「投資収益率」とも呼ばれています。投資によってどれほどの収益を上げられたのか知りたい時、このROIを利用することで、数値化して確認できます。
ROIの計算式は「利益(売上-売上原価-投資額)÷投資額×100」で表され、投資額よりも利益が上回った場合は、100%よりも高い数字となります。一方、投資額よりも利益が少なかった場合は、100%を下回る数字となります。
ここでは「投資額500万円」「売上2,000万円」「売上原価250万円」のモデルケースを例に、実際に計算をしてみましょう。
- (売上2,000万円-売上原価250万円-投資額500万円)=利益1,250万円
- 利益1,250万円÷500万円×100=250%
計算した結果、ROIが250%となり、100%を上回っているため投資に成功したことがわかります。
上記のケースでは、1年間で投資資金を全額回収したことになりますが、実際には数年で回収することもあるでしょう。そのような場合には、100%を下回る額となります。たとえば「当期純利益500万」「投資額3,000万円」のモデルケースを例に挙げると、計算式は以下の通りです。
- 利益500万円÷投資額3,000万円×100=16.7%(小数点第二位以下を四捨五入)
このパーセンテージが毎年続く場合、約6年で投資額を回収できることになります(投資額100%÷ROI16.7=5.98年)。もし、この企業が投資額を5年で回収したい場合は、1年のROIの数値が20%以上でなければならないため、もっと利益を上げる必要があることがわかります。一方、この企業が10年で投資額の回収を目標にしていた場合は、1年間のROIが10%以上であればよいので、目標額を上回っています。
このように、投資額をどの程度の期間で回収したいかによって、ROIの適正な値は変わってきます。投資回収期間を定めてROIを算出することで、毎年の目標利益を打ち出せるのです。
クラウド移行時のROIを考えるための基本パーツ
ROIを算出するためには、投資額や利益、収益をしっかりと計算しなければいけません。ここでは、 クラウド移行 に関わるコスト・利益・収益の計算方法について解説します。
初期投資
クラウドへの移行では主に、クラウドサービス契約料やランニングコスト、システムインテグレーションコスト、運用・管理のための人的コストなどが初期投資に当たります。
このうちクラウドサービス契約料は、契約時に支払う料金をいいます。この料金は、プロバイダによっては無料の場合もあります。
それよりも、毎月の利用料やセキュリティ対策などのランニングコストのほうが大きくなるでしょう。さらにこれらに加え、運用管理に際して人的コストが発生します。どのくらいの規模で運用するのかをしっかりと決めてから、人的コストを算出しましょう。
また、クラウドに移行する際は、システム設計をしなくてはいけません。そのため、要件定義から機能設計といったシステムインテグレーションに関わるコストも発生します。これらすべてが、クラウド移行にかかる初期投資です。
これらは一見すると、多くのコストがかかるように見えますが、オンプレミスのコストと比べて格段に低くなっています。月々の利用料は月額性・従量制から選択でき、運用範囲がオンプレミスよりも狭くなるからです。
投資利益
「投資利益」とは、ここでは「収益」のことを指します。利益は「収益-初期費用」で算出されるため、収益計算が必要となります。しかし、投資利益の計算は複雑なものとなっていて、クラウド移行後に出た収益が「クラウドの恩恵を受けたものである」という理解が必要です。
クラウド移行による収益は、「収益差分+コスト差分」によって計算します。たとえば収益差分は、自社とビジネスの利害関係者と協力して実際に収益が変動したかを予測します。収益への影響が確認できた場合、これを収益差分とします。
一方のコスト差分は、クラウド移行によって生じた金額の増減の差分を指します。これは、運用コスト・資本コスト・減価償却の削減や廃棄資産の販売などが、コスト差分に当たります。
クラウドに移行すると、運用コストが格段に減り、場合によっては人員の削減にも繫がります。「これまで300万円かかっていたコストが150万円になった」などのケースも少なくありません。この差分である150万円が、コスト差分として計算されるわけです。
また、ソフトウェアを無形固定資産とする際、減価償却として扱うことが可能です。企業によっては、この時の税金をコスト差分として扱うことがあります。さらにオンプレミスから移行する場合は、資産を廃棄することがあります。これを販売した場合、収益としてコスト削減に上乗せします。ただしこの場合、売却額に税金がかかるため、計算時には注意が必要です。
このように、さまざまな差分を計算することによって、クラウド移行による当期の利益を算出します。
会計上のクラウドの扱い
従来のオンプレミスとは違い、クラウドにはさまざまなサービス形態があります。サービスごとに会計処理も異なるため、会計処理の際には注意が必要です。
基本的には費用となる
オンプレミスの場合は資産として計上されていましたが、通常クラウドの場合は費用として計上されます。というのも、クラウドではプロバイダが提供するサービスを利用しているため、実際には設備を保有していないからです。
このようなクラウドの会計上の扱いは、2014年に改正された「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」をベースとしています。この中では、ソフトウェア・コンテンツ・データを別のものとして扱っています。そのため PaaS や SaaS 、 IaaS といったクラウドサービスによっても、会計処理が異なるのです。
販売する目的のソフトウェア
SaaSでクラウドサービスを利用して、クラウド上のASPをユーザーに販売する場合、ASPのソフトウェア製作費は研究開発費として費用計上します。研究開発が終了するまでは、費用の発生時に研究開発費として処理することとなります。
研究開発の終了を判断する基準は、「プロトタイプの完成」「プロトタイプを開発しない場合は、製品としての重要な機能が出来上がっていて不具合がないこと」とされています。このあとに改良費がかかった場合は、製作原価として資産計上します。
また、製品マスターは無形固定資産として扱われます。製作原価は製造原価として計上し、完成品と仕掛品は、無形固定資産に振替製造原価から控除しましょう。
自社で利用するソフトウェア
ソフトウェアを自社で利用する場合、費用と資産の計上は状況次第で変わります。ソフトウェアによって、収益の増額やコストカットが確実に見込める場合は、資産として計上できます。例としては、ソフトウェアを自社用に開発したことで、同上のメリットを見込めた場合などが挙げられます。
この時、市販のソフトウェアまたはクラウドサービスのどちらを利用していても、同じように資産として計上できます。また計上時期は、「上記要件を満たすことが確実と認められた時」とされています。
一方、上記のような場合で、収益の増額やコストカットの確実性が見込めない場合は、費用として処理する必要があるため要注意です。
ROIはミクロな部分で考えるべきではない
クラウド導入や移行に際してROIの検証をする場合、細かい部分で算出するには多くの問題があります。細かい部分に目を向けてしまうと、導入後の効果に対する予測が不十分になってしまう恐れがあるのです。
しっかりとした期待効果の指標を算出するためには、導入・運用・サポート体制まで含めた全体を見て行うべきです。たとえば、導入によって大幅なコストカットが見込めたとしても、運用負荷が増大した場合はどうなるでしょうか?
サーバー数が増えたために、優秀な人材を雇用し対応することになったとしたら、当初見込んでいたものよりもコストがかさんでしまいます。試算していたROIを達成できないばかりか、算出した時間が無駄になってしまうこともあります。
クラウド導入におけるROIの検証は、ミクロな視点で考えるのではなく、先々を見据えて試算することで、初めて十分な期待効果を得られるのです。
まとめ
投資に対する採算性を確認するうえで、ROIの活用は有効な手段といえます。しっかりと計算して算出すれば、企業経営の役に立つでしょう。
しかし、クラウド導入に関する収益の計算は難しいものがあります。適切なROI管理を心がけ、クラウドへの円満な移行を目指しましょう。